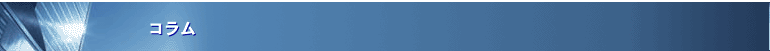経済産業省の産業構造審議会・人材育成ワーキングでも、融合人材について議論がされました。また、現在進行中の内閣官房の議論でも、次世代のIT人材が注目されています。今回はこれらについて深堀りしてみます。
|
|
|
今後必要な人材の推移 |
大きな流れで言えば、クラウド・コンピューティングなどシステムを開発せずに、用意されたものを組み合わせて使うような考え方に、急速に移行しています。当然IT人材に要求されるスキルそのものも変わっていくことになります。
以下にここしばらく前の状況からの変化を、大きな観点で羅列してみます。
・労働集約型(人海戦術) から知識集約型へ
下流のオフショア化
下流の自動化ツール
・環境の変化によるターゲットの遷移から短期開発の必要性増大
企画/開発/運用サイクルの短期化
開発のスピード、高品質
もしくは、開発せずに組み合わせる技術(センス?)
・開発効率化、機能向上から新しい価値の創造の考え方へ
ビジネスモデル創出の多様性
既存の価値にとらわれない自由な思考力、発想力
多様性や異なる価値観に対する需要性、理解力
未来ビジョン構築力 |
|
|
「プロデューサー」の考え方 〜産業構造審議会 |
 産業構造審議会でも議論になったのが、「プロデューサー」の位置づけです。プロデューサーは、事業創造からその仕組みの構築、運用に至るまで広範囲なエリアを対象とした人材になります。 産業構造審議会でも議論になったのが、「プロデューサー」の位置づけです。プロデューサーは、事業創造からその仕組みの構築、運用に至るまで広範囲なエリアを対象とした人材になります。
定義文は次の通りです。
「試行錯誤の段階から、価値発見段階、サービスデザイン段階、そして事業創造段階と各段階を通して、新しい事業における全体を統括する人材であり、事業全体の中心をなす職種」
これだけでは抽象的で分かりづらいのですが、範囲の一部として図とも提示されています。 |
|
|
プロデューサーの定義 |
現実的に考えると、ユーザー企業のビジネス目標達成を支援する前提となるので、ユーザー企業、ITサービス企業双方の役割分担になると考えられます。
ユーザー企業
・ユーザー企業においてIT活用をした新たなビジネスそのものを立案し、実現できる人材
・従来のようなITによる効率化を超えて、ITによる新たなビジネス創出を実現できる人材
ITサービス企業
・ユーザー企業とともに、ITを活用した新たなビジネスを考案し、その実現をサポートできる人材
・ITサービス企業自ら、(従来の受託開発型ビジネスを超える)新たなビジネスを考案し、それを
開拓・実現できる人材
総じて
「新規事業創出を主体的に担える人材」
と定義することができます。
〜その3につづく |
|
|
|
|
登録:2014-04-16 10:54:44
|